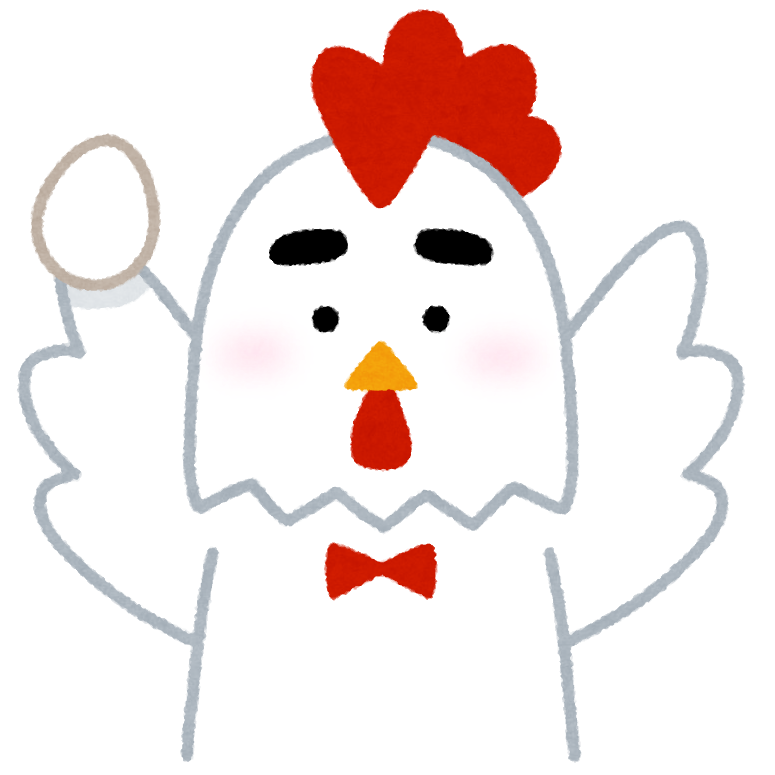「キュレーターの殺人」のなかで、主人公のひとり「ティリー・ブラッドショー」が捜査官たちを相手にプレゼンしている場面があります。
捜査官のひとりが「卵が先か、ニワトリが先かってことだな」というようなことを言います。
もちろん「どちらが原因として先にあるか分からない」という比喩的な意味で使ったのですが、ティリーは「どういうこと?」と聞き返します。
科学オタクのティリーにとって、それはもう解決済みの問題だったらしいのですね。
「ニワトリが先でしょ」
ティリーの説明はこうでした。
卵の殻とニワトリの卵巣の両方に含まれる、あるタンパク質があります。
ある研究チームが、ニワトリの卵巣の中にこのタンパク質が存在しなければ、卵ができないことをつきとめたのでした。
つまり、ニワトリが先にいなければ「ニワトリの卵」はできないということです。
その捜査官は「そ、そうなのか?」と、すっかり打ちのめされてしまうというシーンなのでした。
その話の元となった、実際の論文(というかニュース)はこれです。
「Researchers apply computing power to crack egg shell problem」
https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/researchers_apply_computing/
ウォーリック大学とシェフィールド大学の研究者たちが、卵の殻がどう形成されるのかを解明したというものです。
実は、この研究の目的は「卵が先か、ニワトリが先か」を明らかにすることではないのですね。
研究者たちは卵の殻を形成する過程をシミュレーションし、そのメカニズムを明らかにしたものです。
過程のなかで、先にティリーが説明した、タンパク質「ovocledidin-17」の発見が大きなトピックになったのでした。
科学オタクたちが、この話に飛びついたのはお察しの通りです。
「卵か先か、ニワトリが先かの古来からの大問題がついに解決した!」と。
しかし、当の研究者自身は、もちろんそんなつもりで研究していた訳ではないのですから、「決定的なこたえが出たわけではない」と言っています。
ちなみに、生物学者は、進化生物学的には「卵が先だ」と言っています。
なぜなら、硬い殻を持つ卵は、太古の昔に有用膜類の動物たちが成し遂げた一大革命だからです。
この有用膜類とは、爬虫類、鳥類、哺乳類などを含む動物たちのことで、これらの動物は胎児と羊水を包む胚膜、いわゆる「有用膜」を持っています。
この有用膜があることで、地上の乾燥に適応した硬い卵が産めるようになったのです。
しかし、この問題は卵をどう定義するかで答えが変わります。
もし最初のニワトリが生んだ卵の話をしているのなら、答えは逆転します。
遺伝学の観点から見れば、その最初のニワトリはまだニワトリとは呼べない種の突然変異によって誕生したはずです。
つまり、この突然変異体が成長して大人になった鳥が最初のニワトリであり、その鳥が生んだ卵こそが最初のニワトリの卵なのだから、この場合の答えは「ニワトリが先」となります。
このように、問題の解釈によって答えは変わるのです。
ただ、人がこの問題に興味を持つのは、単に答えを知りたいからだけではないでしょう。
この問題は、因果関係や起源、進化といった、人類が永遠に答えを求め続ける大きなテーマに触れているからです。
そして、その答えが一つでないことが、この問題をより深く、そして永遠のものとしています。