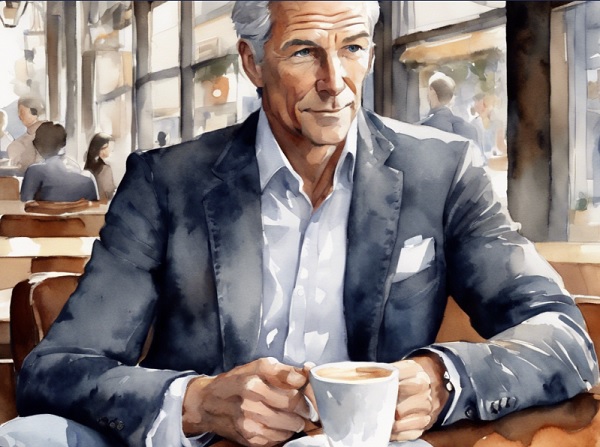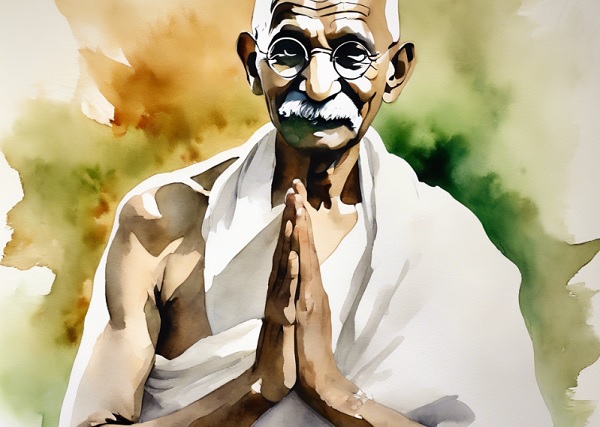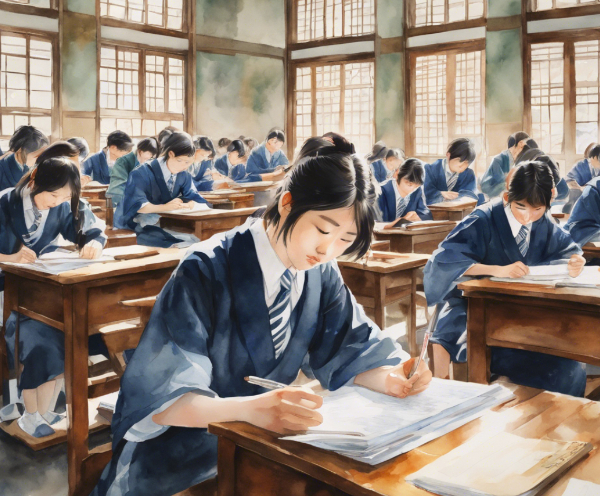透析治療を受けている人々にとって、骨の健康は大きな問題です。
腎臓のはたらきが低下してくると、ビタミンDや副甲状腺ホルモン、それとカルシウムやリンが組成に大きく関連する骨の間で、そのバランスを保つために、通常とは違った変化が起こってきます。
そのひとつが、二次性副甲状腺機能亢進症(SHPT)で、骨密度(BMD)の低下と密接に関係しています。
治療法としては、副甲状腺摘出術とシナカルセトという薬剤がありますが、これらの治療法がBMDにどのような影響を与えるか、直接比較した研究はまだ少ないのが現状です。
香港の2つの大学病院で行われた前向きパイロットオープンラベル無作為化試験は、この重要な問いに光を当てたものです。
65名の腹膜透析患者が参加し、一方のグループは副甲状腺摘出術を、もう一方のグループはシナカルセトを12ヶ月間使用しました。
研究の目的は、これらの治療が骨密度に与える影響を明らかにすることでした。
結果は興味深いものでした。
両方の治療法で腰椎と大腿骨頚のBMDが有意に改善されましたが、副甲状腺摘出術を受けたグループでは、シナカルセト治療グループよりもBMDの増加が顕著でした。
特に、腰椎と大腿骨頚における骨粗鬆症/骨減少症の割合は副甲状腺摘出術グループで有意に減少し、この点においてシナカルセト治療グループとの違いが明確になりました。
しかし、遠位橈骨(手首の近くの骨)のBMDには、どちらの治療も有意な影響を与えませんでした。
これは、治療法が骨の異なる部位に異なる影響を与える可能性があることを示しています。
研究の限界もあります。
骨組織の直接的な評価が行われなかったことや、研究期間が12ヶ月と比較的短期間であること。
これらの点を考慮に入れつつも、この研究は、進行したSHPTを持つ腹膜透析患者における骨密度管理に関して、重要な示唆を与えています。
この研究は、進行したSHPTの管理における治療法の選択肢について、新たな知見を提供しています。
しかし、今回の結果はあくまでパイロット試験のものであり、より長期間にわたる研究や、骨組織の評価を含むさらなる研究が望まれます。
また、骨の健康を維持するためには、骨密度だけでなく、患者の全体的な健康状態や生活習慣にも注意を払う必要があります。
たとえば、適切な栄養摂取、定期的な運動、禁煙といった生活習慣の改善も、骨の健康にとって重要です。
副甲状腺摘出術はより積極的な介入であり、一方でシナカルセトは薬剤治療としての選択肢を提供します。
当然ながら、患者さんと医療チームが共同で、最適な治療方針を決定することが大切です。
元論文:
Wang AY, Tang TK, Yau YY, Lo WK. Impact of Parathyroidectomy Versus Oral Cinacalcet on Bone Mineral Density in Patients on Peritoneal Dialysis With Advanced Secondary Hyperparathyroidism: The PROCEED Pilot Randomized Trial. Am J Kidney Dis. Published online November 30, 2023. doi:10.1053/j.ajkd.2023.10.007